大発生したアオミドロ駆除から2週間経過
アオミドロと思われるコケにまみれた立ち上げ直後の新40センチ水槽ですが、その後どうなったのか投稿したいと思います。
まずはこちらの写真を見てください。

流木に着いたウィローモスがまたもやコケまみれになりました。それでも光合成はしているようで気泡がコケにしっかりホールドされ、一見クリスマスツリーのような感じになっています。
見にくいですが、写真左にあるロタラインディカにもたっぷりとコケが絡んでいます。
原因究明はさておき、まずは掃除です。
ロタラインディカ、ハイグロフィラポリスペルマ、ウィローモス付き流木を外に出した後の状態がこんな感じでした。底床にもビッシリコケが生えていました。

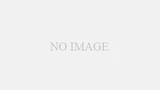
このままコケの大草原を作ってやろうかと思うくらいの状態でしたが、見栄えがよろしくないので、プロホースでガシガシ底床を掘って、水替えと共に出来るだけコケを吸い出しました。
次に水槽から取り出した水草を水の入ったバケツに入れて、指で葉を優しく撫でてコケの除去、そしてコケの着きが酷い葉や茎はバッサリ切り落としました。この辺は前回の投稿で行ったことと全く同じです。
掃除の終わった水槽はこんな感じになりました。

ウィローモスも輝きを取り戻しました。

とりあえずは綺麗になった感じです。
コケの発生が収まらない原因は???
コケ発生の一番の理由は「水の富栄養化」ということは有名な話です。しかし、私の水槽はあまり多くの餌を与えていないので、エサのやりすぎによる富栄養化は考えにくいです。
では、なぜコケの育成に使われてしまう養分があるのか? これには「リービッヒの最小律」が絡んでいるのはないかと推察します。
リービッヒは、植物は窒素・リン酸・カリウムの3要素が必須であるとし、生長の度合いは3要素の中でもっともあたえられる量の少ない養分によってのみ影響され、その他2要素がいくら多くても生長への影響はないと主張した。後に養分以外の水・日光・大気などの条件が追加された。
現在では、それぞれの要素・要因が互いに補い合う場合があり、最小律は必ずしも定まるものではない、とされている。
つまり、上記の3要素がバランスよくないため、どれかが余り、それがコケの育成に使われてしまっているということです。一般的に飼育水内はカリウムが不足しやすいと言われています。
ということで、かなり月並みではありますが、コケの発生を抑える対策は
- カリウムを定期的に足す。
- Co2を添加して水草の育成を促進させる。
- 水換えの頻度を増やす。
となります。最近、CO2の添加をちょっとサボっていたのでまた定期的に添加をしていきたいと思います。
(私のCO2添加装置はこちら↓)

まとめ
コケがガシガシ発生してくると凹みますね。。。 がんばって対策していきたいと思います。そろそろエビや貝といった生物を投入してコケの抑制を行うことを考えてみてもいいのかもしれません。。
あと、報告するほどの話ではないですが、先日の大量発生アオミドロ駆除の後、コリドラス・ステルバイを2匹購入しました。コリドラスは動きやフォルムがカラシン系の魚たちと異なるので水槽の内のアクセントとなり良いですね。うちの子供たちも気に入っています。



コメント